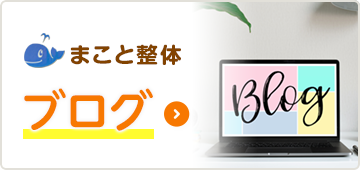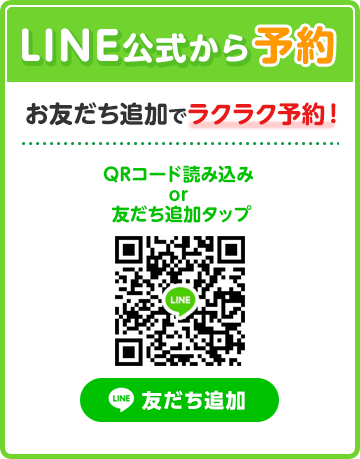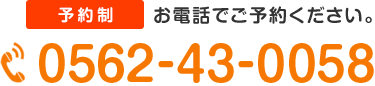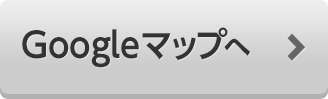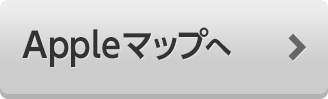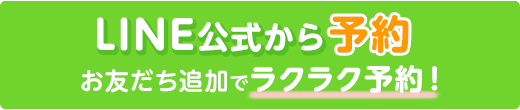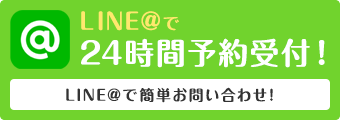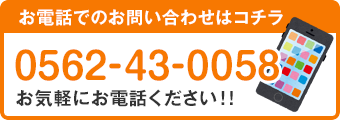2025/09/16 (更新日:2025/09/25)
腹部脂肪増加による体の影響
腹部の脂肪が増加すると骨格筋のバランスが失われさまざまな体の不調を引き起こします。
ねこぜ、肩こり、腰痛、股関節痛、膝関節痛、足関節痛など
<引き起こしやすい症状と疾患>
内臓下垂、メタボリックシンドローム
高血圧、脂質異常、動脈硬化などにより糖尿病、心筋梗塞、脳卒中の原因となる。
脂肪肝、膵炎、睡眠時無呼吸症候群など
全身にわたり健康が損なわれるので腹部の脂肪増加にならないように気をつけましょう!
今回は骨格筋の不調を引き起こす症状を6つ挙げていきます。
1.ねこぜと姿勢悪化
背中が丸くなる。
胸筋、腹筋、背筋、脇腹筋の筋力が低下する。
内臓の機能が低下して内臓の位置がずれてくる。
基礎代謝量が低下して新陳代謝がおちる。
2.肩こり
胸筋、肩部、背部の筋肉を筋肉硬直を発症する。
ねこぜと巻き肩が形成されてしまう。
腹筋、背筋、脇腹筋の筋力が低下する。
肩こり慢性により首痛み、頭痛の原因となる。
3.腰痛
腹筋、背筋、脇腹筋の筋力が低下する。
反り腰形成、骨盤が後傾し骨盤が歪み体のバランスが失われる。
腰椎の狭窄と腰回りの筋肉硬直を発症する。
腰痛慢性により脚の痛み、しびれの原因となる。
4.股関節痛
骨盤が後傾し骨盤が歪み体のバランスが失われる影響が股関節痛の不調につながります。
臀部(お尻の筋肉)の筋力が低下する。股関節の可動域が狭まる。
骨盤後傾によりがに股が形成されてしまう。(歩き方が変わってしまう。)
5.膝関節痛
骨盤が後傾し骨盤が歪み体のバランスが失われる影響が膝関節の不調につながります。
ハムストリングス(太もも後ろ)が硬くなり、膝裏の筋肉が硬くなる。
関節面に負荷がかかり、膝関節の軟骨摩耗につながる。
膝関節の伸ばしにくくなる。o脚が形成されてしまう。
6.足関節痛
骨盤が後傾し骨盤が歪み体のバランスが失われる影響が足関節の不調につながります。
関節面に負荷がかかり、足関節の軟骨摩耗につながる。
体の重心が変わり、床地面を踏ん張る力が弱くなる。
立位、歩行時のバランス感覚が低下して転倒しやすくなる。
上記のような全身の不調を起こさない健康体を維持させるためにも
腹部脂肪を増加させない予防と対策が大切になります。
次回(10月上旬)は腹部脂肪増加の予防と対策をお伝えしていきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。